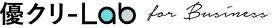「かっこいいデザインを依頼したのに、可愛らしいものが納品された」
「高級感を求めたのに、安っぽく見えてしまう」
デザイナーにデザインを依頼した際、このような経験はありませんか?せっかく時間とお金をかけて依頼したにもかかわらず、完成したものがイメージと異なると、落胆してしまうものです。なぜこのような「イメージと違う!」という事態が起こってしまうのでしょうか?
デザイン発注者としては、デザイナーに自分のイメージを正確に伝え、期待通りのデザインを納品してもらうことが不可欠ですが、デザインのイメージは非常に抽象的で、言葉で表現するのが難しいものです。そのため、「かっこよく」「おしゃれに」といった曖昧な表現で伝えてしまうと、デザイナーとの間に認識のずれが生じ、結果としてイメージと違うデザインが納品されてしまうのです。
この記事では、デザイン発注で失敗しないために、発注者が知っておくべき言語化とイメージ共有のコツを詳しく解説します。これらのコツを実践することで、デザイナーとのコミュニケーションが円滑になり、理想のデザインを実現できます。また、デザイン発注時によくあるトラブル事例と対策についても解説しますので、安心してデザイン制作を進めることができるでしょう。
\デザイナー・クリエイター採用のプロフェッショナルをお探しですか?/
ユウクリは、プロのデザイナー・クリエイターに特化した人材エージェンシーです。
採用の課題に寄り添い、貴社のニーズに最適な即戦力人材をご紹介します。
1.デザインイメージとは?共有を難しくする3つの原因
デザインイメージとは視覚的な印象や感覚のことです。色、形、配置、質感など、様々な要素が組み合わさって構成されており、言葉だけで完全に表現するのは難しいものです。
このデザインイメージの共有を難しくする原因は3つあります。
1.言葉の曖昧さ
「おしゃれ」「スタイリッシュ」「モダン」といった言葉は、日常会話ではよく使われますが、デザインの現場では非常に曖昧な表現です。これらの言葉は人によって解釈が異なり、デザイナーとの間で認識のずれが生じやすいのです。
例えば、「おしゃれ」という言葉一つとっても、可愛らしいものを想像する人もいれば、洗練されたものを想像する人もいます。このように、抽象的な言葉だけを使ってイメージを伝えようとすると、デザイナーは発注者の意図を正確に理解することができず、結果としてイメージと違うデザインが出来上がってしまうのです。
2.認識のずれ
発注者とデザイナーは、それぞれ異なる経験や背景を持っています。そのため、同じ言葉を聞いても、連想するイメージが異なる場合があります。
例えば、発注者が「高級感」という言葉を使ったとしても、デザイナーが過去に触れてきた高級なデザインと、発注者が想像している高級なデザインが異なれば、認識のずれが生じてしまいます。このような認識のずれは言葉だけでなく、文化的な背景や個人の好みなども影響するため意識的に解消していく必要があります。
3.情報不足
デザイナーに伝えるべき情報が不足していると、デザイナーは十分な情報を得られず、発注者の意図と異なるデザインを作成してしまう可能性が高くなります。
例えば、ターゲット層、デザインの目的、使用する媒体などの情報が不足していると、デザイナーはどのようなデザインを作成すべきか判断に迷ってしまいます。情報不足は、デザインの方向性を大きく左右するだけでなく、修正の手間と時間を増やす原因となります。

2.デザイナーに意図を100%伝えるための言語化/イメージ共有のコツ5つ
デザインイメージの共有は様々な要因で難しくなることがありますが、以下の5つのコツを実践することで、デザイナーに意図を100%伝え、理想のデザインを実現することが可能です。
コツ1:イメージが伝わる言葉を選ぶ
言語化する際は、曖昧な表現をできるだけなくし、具体的な言葉を使うことを意識しましょう。抽象的な言葉ではなく、「色:青、濃いネイビー」「フォント:ゴシック体、太字」「レイアウト:左右対称、余白多め」など、具体的な言葉で表現することが重要です。
形容詞リスト
デザイン表現に役立つ言葉を集めました。イメージを言語化する際の参考にしてみてください。
| 要素 | 言葉 |
|---|---|
| 雰囲気 | モダン、クラシック、エレガント、ポップ、クール、シャープ、力強い、洗練された、温かみのある、ナチュラル、オーガニック、ラグジュアリー、ミニマル、レトロ、ヴィンテージ、アーティスティック、ユーモラス |
| 色 | 明るい、暗い、鮮やか、落ち着いた、パステル、ビビッド、メタリック、マット |
| 形 | 丸い、四角い、直線的、曲線的、幾何学的、有機的 |
| 質感 | 滑らか、ざらざら、つややか、マット、重厚、軽快 |
これらの形容詞を知ったうえで、伝える時は具体的な表現にできるとベターです。次でご紹介します。
具体的な表現例
NG例とOK例を比較してみましょう。
| NG例 | 「かっこよく」「おしゃれに」「いい感じに」 |
|---|---|
| OK例 | 「色は黒とシルバーを基調に、メタリックな質感で、フォントはゴシック体、太字で力強い印象にしてください。レイアウトは左右対称で、余白を多めに取り、洗練された雰囲気にしてください。」 |
このように、具体的な言葉で表現することで、デザイナーは発注者の意図を正確に理解できます。
コツ2:視覚資料を活用する
言葉だけでは伝わりにくいニュアンスも、具体的なデザインを見せることで伝えられます。
参考のWebサイト/デザインURL
伝えたいイメージに近いWebサイトやデザインのURLを共有することで、視覚的に意図を伝えられます。その際は、Webサイト全体の雰囲気だけでなく、「ロゴのデザイン」「配色の組み合わせ」「レイアウトの構成」など、どの部分を参考にしているのかを具体的に伝えるようにしましょう。
Pinterest/Behanceなど画像共有サービス
PinterestやBehanceなどの画像共有サービスを活用して、イメージボードを作成するのも有効です。複数の画像を組み合わせて、伝えたいイメージを視覚的に表現できます。
イメージボードを作成する際は、単に画像を並べるだけでなく、キャプションでそれぞれの画像の意図を補足することで、より正確に意図を伝えられるでしょう。
手書きのラフスケッチ
簡単な図でも、手書きのラフスケッチを作成することで、デザインの方向性を伝えることができます。完璧なスケッチである必要はありません。大まかなレイアウトや要素の配置などを伝えるだけでも、デザイナーの理解を深める効果があります。
カラーパレット/色見本
使用したい色を具体的に伝えることで、色の認識のずれを防ぐことができます。カラーパレットや色見本を共有することで、デザイナーは発注者の意図する色を正確に把握することができます。
海外のサイトですが、「Color Hunt」のようなユーザーから人気の配色パターンをまとめた色見本のサイトもあるので参考にしてください。
コツ3:デザインコンセプトシートを作成する
デザインコンセプトシートは、デザインの目的やターゲットなどを明確にすることで、デザインの方向性を定めることができるイメージ共有のためのツールです。デザイナーと共有することで認識のずれを防ぎ、スムーズに制作を進めることができます。
コツ4:デザイン要素を分解して伝える
デザインの構成を各要素に分解し、それぞれについて具体的な指示を出すことで、デザイナーへの伝達精度を高められます。
以下にいくつか例を挙げます。
| 要素 | 指示内容 |
|---|---|
| 色 |
|
| フォント |
|
| レイアウト |
|
| 画像 |
|
| アニメーション |
|
| インタラクション | ユーザーの操作に対する反応(例:マウスオーバー時の変化、クリック時の遷移など)を指定 |
コツ5:コミュニケーションを取る
制作過程では、デザイナーとの密なコミュニケーションを心がけましょう。疑問点や不明点があれば遠慮せずに質問し、認識のずれがないかを確認することが重要です。
デザイナーへの質問リスト
デザインの方向性や制作プロセスについて質問することで、発注者とデザイナー双方でお互いの理解を深めることができます。以下、デザイナーへの質問例をいくつか挙げます。
- デザインの方向性について、他に提案はありますか?
- 修正は何回まで可能ですか?
- 納品データ形式は何ですか?
- 使用する素材(写真、イラストなど)はこちらで用意する必要がありますか?
- 完成までのスケジュールはどのようになっていますか?
コミュニケーションツールの活用
チャットツール(Slack、Chatworkなど)、オンライン会議ツール(Zoom、Google Meetなど)など、適切なコミュニケーションツールを活用することで、スムーズな情報共有と意思疎通を図れます。
フィードバック
デザイン制作の途中経過を確認する際には、建設的なフィードバックを心がけましょう。感情的な表現は避け、具体的な改善点を指摘することで、デザイナーは的確に修正を行うことができます。
例えば、「なんか違う」という抽象的な表現ではなく、「この部分の色をもう少し明るくしてほしい」「フォントをもう少し太くしてほしい」など、具体的な指示を出すようにしましょう。また、代替案を提示することで、よりスムーズに意図を伝えることができます。

3.デザイン発注時の注意点
デザイン発注時には、以下の点に注意することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
3-1.一人ではなく複数のデザイナーに見積もりを依頼する
複数のデザイナーに見積もりを依頼することで、相性の良いデザイナーを見つけやすくなります。また複数の提案を受けることで、より良いデザイン案が見つかる可能性があり、デザインの幅を広げることもできます。
ポートフォリオで見るべきポイント
デザイナーのポートフォリオを見る際には、デザインスキルだけでなく、コミュニケーション能力や対応力なども考慮に入れるようにしましょう。過去の制作実績だけでなく、クライアントとのやり取りや制作プロセスなども確認できると、より深くデザイナーを理解することができます。
相性の見極め方
デザイナーとの相性を見極めるためには、実際にコミュニケーションを取ってみることが重要です。レスポンスの速さ、コミュニケーションのスムーズさ、提案力などを確認し、信頼できるデザイナーかどうかを判断しましょう。
3-2.トラブル防止のために契約書を交わす
デザイン発注時には、必ず契約書を交わすようにしましょう。契約書には、著作権、納品物の種類、修正回数、納期、報酬、支払い条件など、重要な項目を明記することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
契約書に記載すべき項目
契約書には、以下の項目を記載することをお勧めします。
- 著作権の帰属
- 納品物の種類と形式
- 修正回数と範囲
- 納期
- 報酬と支払い条件
- 秘密保持義務
- 契約解除に関する事項
4.その他よくあるトラブル事例と対策
最後にデザイン発注時によくあるトラブル事例と、その対策について解説します。
事例1:修正回数が多い場合
修正回数が当初の想定よりも多くなってしまう場合は、事前に修正回数やフィードバック方法について合意しておくことで、トラブルを避けられます。また、修正が必要な場合は、イメージの共有が足りていないかもしれません。ご紹介した5つのコツを参考に具体的な指示を出すように心がけましょう。
事例2:著作権に違反している場合
デザイナーが著作権に違反している素材を使用していた場合、発注者側も責任を問われる可能性があります。もし違反していた場合はまずは修正を促しましょう。それでも十分な修正対応がされない場合は、交わした契約書を元に法律関連の専門家とともに対応を協議する必要があります。
事例3:連絡が取れなくなった場合
デザイナーと連絡が取れなくなってしまった場合は、契約書に記載されている連絡先や緊急連絡先に連絡してみましょう。それでも連絡が取れない場合は、弁護士などに相談することも検討してください。
まとめ 手間をかけずイメージに合うデザインを作るならユウクリへ
デザイン発注は、適切な準備とコミュニケーションによって成功します。この記事でご紹介した以下5つのコツと発注時の注意点を参考に、ぜひ理想のデザインを実現してください。
【イメージ共有のための5つのコツ】
- イメージが伝わる言葉を選ぶ
- 視覚資料を活用する
- デザインコンセプトシートを作成する
- デザイン要素を分解して伝える
- コミュニケーションを取る
【実践チェックリスト】
- デザインの目的とターゲット層を明確にしたか?
- 伝えたいイメージを具体的な言葉で表現できているか?
- 参考になるWebサイトやデザイン、画像などを集めて共有したか?
- デザインコンセプトシートを作成したか?
- 各デザイン要素について具体的な指示を出せるか?
- デザイナーと密にコミュニケーションを取る準備ができているか?
- 複数のデザイナーに見積もりを依頼して相性の良さを確認したか?
- 契約書の内容を十分に詰められているか?
とはいえ、自社でデザイナーを探したり、コミュニケーションを取ったりする時間やノウハウがないという方もいらっしゃるかもしれません。そんな時は、デザイナー専門の人材サービス「ユウクリ」にご相談ください。
ユウクリには3.7万人以上のプロのデザイナーが在籍しており、派遣・正社員・業務委託など、お客様のニーズに合わせた契約が可能です。決定実績2万件以上、取引社数7,000社以上という豊富な実績があり、ユウクリが間に入ることでデザイン発注に伴う工数の削減はもちろん、トラブル予防・発生時の対応もしてくれるため安心して効率よくデザイン制作を進められます。デザインに関するお困りごとがあればぜひユウクリをご検討ください。