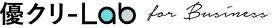「AIで記事を量産しているが、コアアップデートで順位が急落してしまった…」
「AIの進化は目覚ましいが、SEOにおいて本当に活用して良いものなのだろうか?」
「Googleの評価基準が変わるたびに、自社のSEO対策が正しいのか不安になる」
日々めまぐるしく変化するGoogleのアルゴリズムやAI技術の進化に対し、企業のWEB・SEOご担当者様は、このような不安やお悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
特に、検索順位に大きな影響を与える「Googleコアアップデート」は、サイトの「信頼性」や「ユーザーにとっての価値」を根本から問い直すものであり、小手先のテクニックや単なるコンテンツの量産といった従来の手法が通用しづらくなっているのが実情です。
この記事では、「AI記事の順位はなぜ下落するのか?」という疑問を解き明かすため、その大きな要因であるGoogleコアアップデートの本質と、AIコンテンツとの関係性を深掘りしていきます。
\WEBマーケティングご担当者様向け/
【Googleのルール変更のポイントと今後の変化予測】
無料ダウンロード
Googleコアアップデートとは? なぜ「AI記事」の順位と関係するのか

まず基本として、Googleコアアップデートがどのようなもので、なぜ重要視されるのかを正しく理解することが、AI記事とSEOの関係を考える上での第一歩となります。
検索順位の「教科書」の大規模な見直し
Googleコアアップデートとは、一言でいえば、Googleが検索結果の品質を向上させるために実施する、検索順位を決定するための評価基準(アルゴリズム)の大規模な見直しのことです 。 Google自身はこれを「教科書のようなルールの大きな見直し」と表現しており、年に数回、不定期に実施されます 。
このアップデートがなぜ重要かというと、評価の「教科書」が変わることで、これまで検索結果の上位に表示されていた自社サイトの順位が、ある日を境に大きく下落したり、逆に上昇したりといった、劇的な変化が起こりうるからです 。
そのため、WEBサイトを運営し情報発信を行う全ての企業にとって、このルール変更の本質を理解しておくことは極めて重要と言えます 。
コアアップデートが目指す「ユーザーファースト」の世界
では、Googleはなぜ頻繁に「教科書」を見直すのでしょうか。その根底にある目的はただ一つ。「ユーザーにとって、より有益で信頼できる情報を、より簡単に見つけられるようにする」ためです 。
Googleが掲げる「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる」という理念にすべてが集約されています 。つまり、コアアップデートとは、検索エンジンを騙すようなSEOテクニックを排除し、真にユーザーの役に立つコンテンツを正当に評価するための、いわば「検索体験の品質向上活動」なのです 。
この目的を理解するとAI記事との関係性が見えてきます。 Googleの評価基準は「人間が書いたか、AIが書いたか」という生成方法にはありません 。そのコンテンツが「ユーザーにとって有益で、信頼できるか」という品質ただ一点で判断されるのです 。
なぜAI記事の順位が下落するのか? 2つの主要因
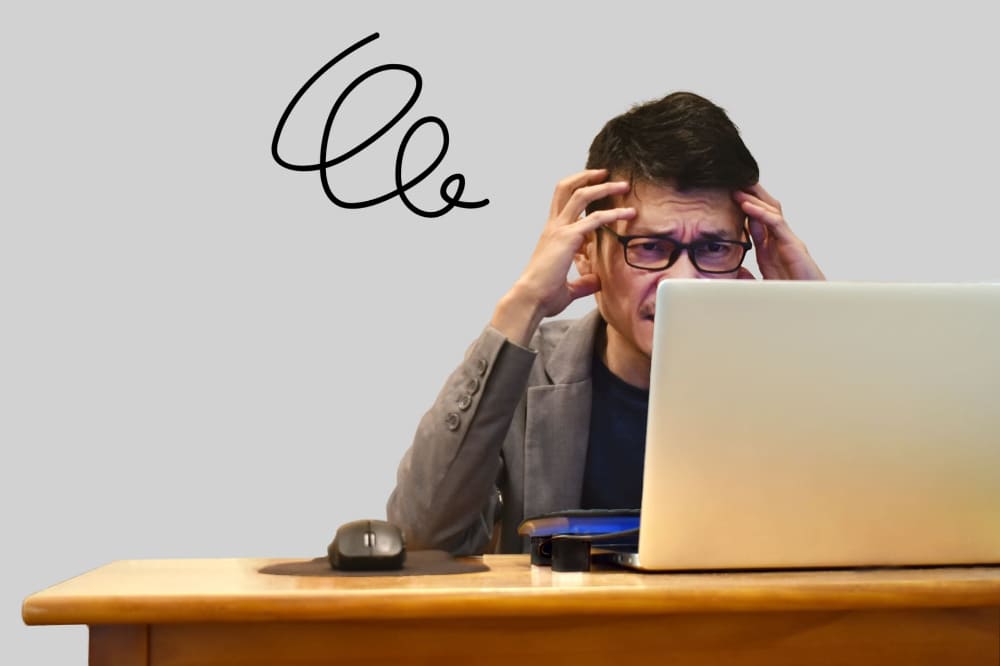
「AIが作ったからという理由だけで順位が下がることはない」 これは Googleが公式に発信している見解であり、事実です 。現に、AIを活用して制作した記事でアクセスを大きく伸ばしている企業も存在します 。
しかしその一方で、コアアップデートを機にAIで制作した記事の順位が急落したり、圏外に飛ばされたりするケースが後を絶たないのも事実です 。
この差はどこから生まれるのでしょうか。その主要因として、近年のコアアップデートで特に重視されている2つの評価軸が挙げられます 。
主要因1:Googleが最重要視する「E-E-A-T」の欠如
コアアップデートの評価基準を語る上で、絶対に欠かせないのが「E-E-A-T」という概念です 。これは「経験・専門性・権威性・信頼性」の頭文字を取ったもので、Googleがコンテンツの品質を測る上で最も重視する指針の一つです 。
- Experience(経験): そのトピックについて、筆者が実体験や人生経験を持っているか。
- Expertise(専門性): そのトピックについて、筆者が専門的な知識やスキルを持っているか。
- Authoritativeness(権威性): その分野において、筆者やサイトが第一人者として認識されているか。
- Trustworthiness(信頼性): 情報が正確で、サイトや運営者が信頼できるか。
AIは、インターネット上に存在する膨大な情報を学習し、再構成して文章を生成することは得意ですが、AI自身が何かを「経験」することはできません 。
そのため、AIが生成しただけの文章は、どうしても「どこかで見たような情報」の域を出ず、実体験に基づいた独自の考察や一次情報を含まない、E-E-A-Tの低いコンテンツになりがちです 。
Googleは「誰が、どんな経験や専門性を持って情報を発信しているのか」という点を、これまで以上に厳格に評価しています 。 順位が下落するAI記事の多くは、このE-E-A-T、特に「経験(Experience)」と「信頼性(Trustworthiness)」の観点が決定的に欠如しているケースがほとんどです 。
主要因2:「ヘルプフル コンテンツ システム」の評価基準
もう一つの主要因が、「ヘルプフル コンテンツ システム」です 。これは、「ユーザーを第一に考えて作成された、役に立つコンテンツ」を高く評価し、逆に「検索順位を上げることだけを目的として作られたコンテンツ」の評価を下げるための仕組みです 。
AIの能力向上により、特定のキーワードを盛り込み、一見すると網羅性が高く見える記事を短時間で大量に作れるようになりました 。しかし、そうした記事の多くは、以下のような「ユーザーの役に立たない」特徴を持っています 。
- 当たり障りのない一般論ばかりで、読者が本当に知りたい具体的な答えがない。
- 情報を羅列しているだけで、独自の視点や深い洞察が欠けている。
- 読後感がなく、「読んでよかった」という満足感を得られない。
このようなコンテンツは、まさに「検索エンジンファースト」で作られたものと見なされ、ヘルプフル コンテンツ システムによって評価が下げられます 。AI記事の順位が下落する背景には、このシステムによる影響も非常に大きいと考えられます 。
「AIだからダメ」は誤解!順位を維持するAI記事の特徴

ここまで読むと、「やはりAI記事はSEOに不向きなのでは?」と感じるかもしれません。しかし、それは早計です 。
重要なのは、Googleのスタンスを正しく理解し、AIを「思考停止のツール」ではなく「優秀なアシスタント」として活用することです 。コアアップデートの影響を受けず、むしろ評価されるAI記事には大きな特徴があります 。
評価されるAI記事に共通する「人間の介在」
評価されるAI記事とは、AIの生成物に「人間の手」が加わっていることです 。
- 専門家による監修・編集: AIが生成した文章の草案を、その分野の専門家がファクトチェックし、専門的な知見を追記・修正する。
- 独自性の付与: AIが作った骨子に、自社独自のデータ、顧客へのインタビュー、担当者の実体験といった一次情報を盛り込む。
- ペルソナへの最適化: AIが生成した一般的な文章を、自社のターゲット顧客(ペルソナ)に響く言葉遣いや構成に編集し直す。
このように、AIを記事制作の効率化を図るための「壁打ち相手」や「リサーチアシスタント」として活用し、最終的な品質担保と価値の付与を人間が行う。この「人間とAIの協業」こそが、これからのSEOコンテンツ制作の鍵となります 。
Googleのルール変更のポイントと今後の変化予測
ここまで、AI記事の順位が下落する背景にあるコアアップデートの本質について解説してきました。 今後もGoogleは定期的にルール変更を行い、検索ユーザーにとって最適な情報を検索結果という形で提供していきます 。
検索結果で上位、特に1ページ目に自社メディアのページが位置するためには、Googleが考える「ユーザーファースト」を表現した記事であり続けることが欠かせません 。
そのためにはどんな対策をしたらいいのか?本記事では十分お伝えしきれなかった「Googleのルール変更のポイントと今後の変化予測」を下記より無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
【Googleのルール変更のポイントと今後の変化予測】
無料ダウンロード
まとめ
Googleのコアアップデートは、今後もユーザーにとってより良い検索体験を実現するために、進化を続けていきます 。 そのたびに検索順位は変動し、一喜一憂することもあるかもしれません 。
しかし、アップデートの本質は常に「ユーザーファースト」です 。目先の順位変動に惑わされるのではなく、自社のコンテンツが「本当にユーザーのためになっているか?」という原点に立ち返り、基本的なポイントを地道に実践し続けることが、最も確実なSEO対策と言えます 。
AIは、そのプロセスを加速させる強力なツールになり得ます 。AIの能力を正しく理解し、人間の強みと掛け合わせることで、貴社のWEBサイトは多くのユーザーに愛され、結果としてGoogleからも高く評価されるはずです 。
もし、「自社だけでの対策に限界を感じる」「専門家の視点からアドバイスが欲しい」という場合は、どうぞお気軽に私たちユウクリにご相談ください。貴社のWEB戦略を成功に導くための、最適なプロ人材をご紹介いたします。