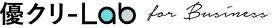今、社会では、これまでのフルタイム勤務に頼った働き方ではなく、それぞれのライフスタイルを尊重する多様な働き方への需要が高まっています。その最たるものが、育児や介護をしながら仕事を両立する働き方でしょう。国もこれらのワークスタイルを強く後押ししており、各種制度の追加や見直しが行われています。この動きを受けて実施された「育児・介護休業法の改正」について、そのポイントをわかりやすく紹介します。
■法改正のポイントと、企業として求められる対応とは?
あまり大きな報道はされませんでしたが、今年の1月(平成29年1月)より『育児介護休業法』及び、関連する『男女雇用機会均等法』が改正施行されています。
この法律は、直接雇用の方だけでなく、パート・アルバイトや派遣社員なども対象となります。
今回の改正においては、「有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和」といった、有期契約労働者に関連する変更もあるのでしっかり把握をしてきましょう。
また、昨今問題となっているマタハラ・パタハラ問題を含む、育児介護休業制度の利用者へのハラスメント行為を防止する措置を行なうことが企業に義務化されている他、このハラスメント行為の防止措置は、派遣社員については、派遣元だけでなく派遣先も事業主とみなし措置を行うことが義務となっているので注意が必要です。
※マタハラ(マタニティハラスメント)
女性社員の妊娠・出産が業務に支障をきたすとして、上司や同僚が退職を促すなどの嫌がらせをすること
※パタハラ(パタニティハラスメント)
男性社員が育児休業制度を活用したりすることに、上司や同僚が妨害、嫌がらせをすること
経営者の方、あるいは現場監督の立場にある方は、今回の改正を受け、しっかりと制度を理解しておくこと、また、就業規則、育児介護休業規程、労使協定、社内の申請書式等の見直しをすることもおすすめします。
文末に厚生労働省が発表した就業規則等の規定例のリンク先をご紹介しておりますので、社内制度整備のための参考としてください。
■介護休業制度の改正内容
1.介護休業の分割取得
【旧】
介護休業について、対象家族1人につき、通算93日まで、原則1回限り取得可能
↓
【改正後】
介護休業について、対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割して取得可能
2.介護休暇の取得単位の柔軟化
【旧】
1日単位での取得
↓
【改正後】
半日単位でも取得可(所定労働時間が4時間超の労働者)
3.介護のための所定労働時間の短縮措置
【旧】
介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能
↓
【改正後】
介護休業とは別に、短縮措置利用開始から3年間で2回以上利用可能
※短縮措置は、以下の内いずれかを選択して行なう
・所定労働時間の短縮
・フレックスタイム制度
・始業終業時刻の繰り上げ繰り下げ
・介護サービス費用の助成
4.介護のための所定外労働の免除
【新設】
介護のための所定外労働の免除(残業免除)を、対象家族1人につき介護の終了まで利用できる
5.有契約労働者の介護休業取得要件の緩和
【旧】
・勤続1年以上あること
・休業開始予定日から93日を経過する日以降も雇用見込があること
・93日経過日から1年を経過する日までに労働契約が更新されないことが明らでない者
↓
【改正後】
・勤続1年以上あること
・93日経過日から6ヶ月を経過する日までに労働契約が(更新される場合は、更新後のもの)満了することが明らかでない者
6.介護休業の対象家族範囲の拡大(省令事項)
【旧】
配偶者・父母・子・配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
↓
【改正後】
同居、扶養していない祖父母、兄弟姉妹及び孫も追加
■育児休業制度の改正内容
7.子の看護休暇の取得単位の柔軟化
【旧】
1日単位での取得
↓
【改正後】
半日単位でも取得が可能(所定労働時間が4時間超の労働者)
8.有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和
【旧】
・勤続1年以上あること
・子が1歳以降も雇用見込があること
・子が2歳までの間に労働契約が更新されないことが明らでない者
↓
【改正後】
・勤続1年以上あること
・子が1歳6か月になるまでの間に労働契約が(更新される場合は、更新後のもの)満了することが明らかでない者
9.育児休業の対象となる子の範囲
【旧】
法律上の親子関係である実子・養子
↓
【改正後】
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子といった法律上の親子関係に準じると言えるような関係にある子についても対象の追加とする
■妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備について
【旧】(育児介護休業法、男女雇用機会均等法)
事業主による不利益取り扱いを禁止
↓
【改正後】(育児介護休業法、男女雇用機会均等法)
・妊娠、出産、育児休業、介護休業等を理由とする、上司、同僚による就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務付ける
※雇用管理上の必要な措置とは、事業主の方針の明確化と従業員への周知・啓発、相談体制の整備、ハラスメントへの対応(懲戒を含む)等
・派遣先で就業する派遣労働者については、派遣先も事業主とみなして、雇用管理上必要な措置を取らなければならない。また、事業主による不利益取り扱いの禁止の規定を派遣先にも適用する
育児・介護休業制度に関する就業規則等の規定例は下記の厚生労働省のページをご参考ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/33.html
今回の改正ポイントと照らし合わせて、既存の社内制度はいかがでしょうか?
きちんと対応できていますでしょうか?
女性が活躍することが多いクリエイティブ業界だからこそ、出産や育児に伴う休業制度を整えることは急務と言えるでしょう。また、チームリーダーや管理職として、優秀な人材には長く活躍してもらいたいからこそ、介護休業制度も充実させておきたいですね。
仕事と育児や介護との両立を企業としてサポートできるような、魅力ある職場作りをぜひ進めていきましょう!