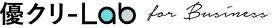仕事の中で、最も時間が取られるといっても過言ではない「企画書」。いいアイデアが浮かんでも企画書に落とし込む段階なると突然気が重くなってしまったり、伝えたいことがうまくまとめられなくて苦手意識を持っている人も少なくありません。初級編に続き、なるべく時間と手間をかけずに、相手を納得させる企画書づくりのコツ、中級編。サクサク通る企画書を作るにはどうすればよいか紹介します。
■コツ1:企画書に「ヌケ」をつくる
いい企画書とは、伝えたい内容がすべて網羅されている企画書です。
しかし、すべてが網羅されている=すべてが書かれているということではありません。
時間をかけ、分厚い企画書に仕上げると、「仕事をした!」という達成感があります。
でも、それは単なる自己満足。受け取った方は、読む気も考える気も失せてしまいます。
よく、会議や打ち合わせで、自身が作成してきた企画書を冒頭からツラツラと読み上げるだけ、という人がいます。
いわゆる「朗読会議」といわれるものです。
しかし、企画書にすべてが書いてあるならば、わざわざ時間をとってミーティングをする必要はありません。それを手渡しして渡して「あとで読んでください」で済んでしまいます。
企画書をつくるときに、念頭におくべきは「企画書はあくまでもプレゼンの資料である」ということです。
あくまでも「話して伝えるための資料」として、必要なもの、そうでなものを精査し、企画書に「ヌケ」をつくっていきましょう。また、「ヌケ」があることで、「これはどういうことだろう?」と相手の興味関心を引き、会議にあなたの話をきちんと聞く環境ができます。
「話せばわかることは企画書に入れない」。
こう決めておくことで、企画書制作の時間がぐっと短縮されます。
■コツ2:使うグラフのデザインを固定する
企画書にグラフを入れる場合、そのデザインによって、伝わるか伝わらないかが大きく変わります。
と言うと、どんなグラフにすればいいか・・・と頭を悩ませてしまい、時間を取られてしまいますが、結局のところ、シンプルなものが一番です。
例えば、円柱や立方体のグラフはデザインとしては目を引きますが、平面グラフのほうが意図は伝わりやすいと言われています。
あらかじめ、自分の企画書に使うグラフを棒グラフならこれ、円グラフならこれ、というようにひとつに決めておきましょう。そうすれば、企画書をつくる際に、グラフデザインで悩むというムダな時間が省けます。
また、グラフに使用する色も事前に決めておきます。
グラフの形と色で悩まない。これだけで、企画書をつくるスピードが格段とアップします。
■コツ3:カッコよさに溺れない
「企画書にキャッチコピーは必要ない」
という発想をもってみてください。
気の利いたコピーを入れようと考えると、悩む時間が増え、その分、手が止まってしまいます。
が、企画書に必要なのは、明確なわかりやすさです。
ふんわりとした、イメージ先行の言葉は企画書の役にはたちません。むしろ、予算や期日の設定など、生々しい要素のほうが重要です。時間をかけるなら、ここです。
どんなに企画書がステキだとしても、その内容が具体性に欠け、現実味がなければ、「いい企画書」とはいえないのです。
優先すべきは、企画書の本質です。それは、企画を通すことです。
そのために必要なものは何か。
企画書の本質に必要のない要素のために時間を割かない。これが、「いい企画書」づくりのコツです。