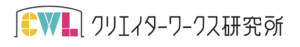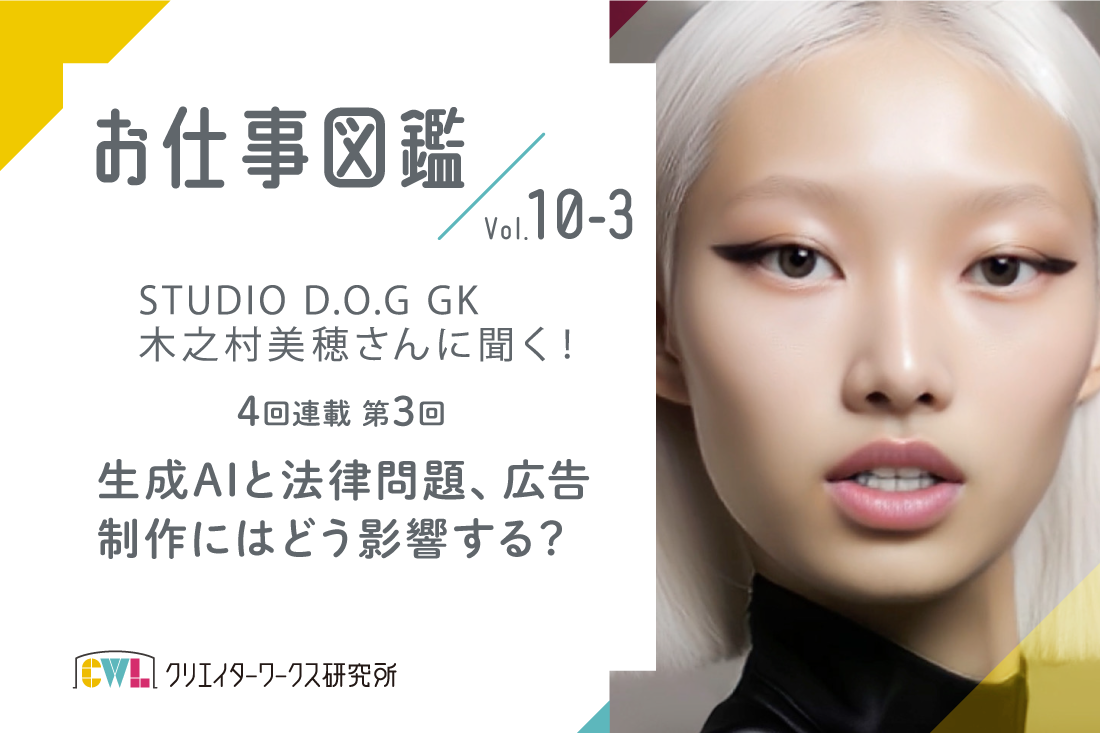こんにちは!クリエイターワークス研究所(CWL)です。
全4回にわたってクリエイティブ業界の最前線で活躍するAIプロンプトディレクターの木之村美穂さんにお話を伺う本企画。
第2回では、AIプロンプトディレクターのお仕事について詳細にお話いただきました。3回目となる今回は、AI業界の動向や法律問題にフィーチャー。気になる“生成AIの著作権問題”についても伺いました。
木之村美穂(Miho Kinomura)さん
STUDIO D.O.G GK 代表
クリエイティブディレクター/ 映像ディレクター/ AI Filmmaker
元ファッションデザイナー Los Angelesを拠点に、広告制作会社の代表として、世界のトップクリエーター達とファッション広告や映像制作に関わる。
2022年からWeb 3.0デジタルメディアに特化した新プロジェクトNFFT(New Future AI Fashion Movie)のAI x Fashion 映像イベントのファウンダーとして、世界で活躍するAI Creator 達を集めたイベントを開催。自らもAI Filmmakerとして、海外のAIフィルムコンテストに参加しAIショートフィルムを海外で発表。2023年12月に発表したPARCO Happy Holidays AI 広告キャンペーンのクリエイティブディレクターとして、日本初のAI 広告をディレクション制作。
Generative AI 関連イベントやセミナーにはアバター miomio として数多く登壇。
必要なのは忍耐と集中力!最先端の技術も、地道な努力で
ーー木之村さんから見て、生成AIに向いている人というのはありますか?
一言で言うと、自分をアップデートできる人ですね。これまでお話ししてきたように、AI業界は今まさに目まぐるしく進化している最中です。常に新しいツールが出てくるし、生成のクオリティも1カ月、2カ月で、大きく進化します。
覚えたと思ったら、また違うことが始まっている。そのくり返しだから、どんどん情報を更新できる人でなければついていけません。
ーー生成AIはアナログなクリエイティブよりもインスタントなイメージがあると思いますが、実際はインプットのための忍耐力や集中力が求められるのですね。
そうです。それに、新しいこと、人がやっていないことをやりたいという好奇心も必要です。素早く学び、学んだことを活用しながら、また新しい情報に意識を向けられる人じゃないと生き残れないですよ。
ーー木之村さんの場合は、どうやって新しいスキルを身につけて新しい情報をキャッチしていますか?

地味ですが、とにかく努力です(笑)スキルを得るのに近道はないので、アンテナを張り巡らせ、ひたすら努力することが大切。
でも、私は苦じゃないんです。新しいことが好きだし、今まで頭の中にあったものが、AIというツールを使うことでカタチになって世の中の人に見てもらえる。非常に面白い仕事だと思っています。
ーーまだ未知数の部分があるからこそ、クリエイター自身の手でAIというツールの可能性を広げられるのですね。
広告制作ではリスクマネジメントが重要。AI周りの法律は今
ーー一方で、AIを使った広告表現により、国内で炎上したものもありますよね。AIが炎上しがちな理由の一つに、著作権や肖像権の問題もあると思います。
その通りです。生成AIの学習に実在の人物や著作物が利用され、学習元に似た画像が生成されてしまう問題は、大きな議論になっています。
ーー木之村さんが制作される時は、どのようにこの問題をクリアにしているのでしょうか。
私が広告を制作する際に気を遣っているのは主に肖像権の問題ですが、いまのところは2つの対策をしています。1つ目は、人物を登場させる際、実在のモデルと契約を結ぶこと。2つ目は、契約時時点の法律を確認し、バックアップをとっておくことです。
ーー1つ目から教えてください。生成AIなのに、実在の人物と契約するとはどういうことですか?
通常のモデルとの広告ビジュアルへの出演契約ではなく、モデルの顔のデータを生成AIに学習させますよという契約です。こうすることで、モデルと似た雰囲気の人物が生成されても肖像権絡みの問題は避けられます。仮にプロンプト(指示文)を開示する必要があっても、契約した人物の名前であれば問題になる可能性は低いんです。
ーーなるほど!人物を生成する時は、具体的にどのような手順を踏むのですか?
まず、スタジオでモデルの顔全体やパーツの写真を大量に撮影します。その後、写真をAIに学習させて人物を生成し、何千枚もの生成された画像から良いものだけを選びます。
出来あがった顔には、クリエイターの手を加える必要があります。画像編集ソフトでメイクやヘアーを施したり、カラーなど部分的に画質を整えたりすることで、広告のクオリティを担保します。
「AIを使う」とは言っても、生成した画像そのままでは広告としては成立しないんですよ。
ーー2つ目の、「バックアップ」について教えてください。
生成AI自体新しいものなので、AIに関する法律も常にアップデートされているんです。あとあと法律が変わってトラブルに発展するのを避けるためにも、広告制作をスタートした時点ではどうだったかということを記録しておくと安心だと思います。

ーー広告制作でAIを使う際、法律の問題以外に気を遣っていることはありますか?
クライアントとの契約ですね。生成AIは人間が想像できないような世界を見せてくれますが、AIならではの表現を面白がるだけでなく、世の中に出すものとして慎重に表現する必要があります。
特に日本の場合、消費者の感想や指摘が大きな問題につながりやすいという背景があります。万が一広告が炎上しそうになった場合も想定して、どう対応するかも含めてきちんと詰めておく必要があります。問題が起こった際に個人では責任を取ることができませんので。
ーーアメリカでエージェンシーを経営している木之村さんから見て、日本と海外でAIを取り巻く環境に違いは感じますか?
まず、国によって法律がちがいますね。日本とヨーロッパでも違いますし、アメリカでも地域によってルールが異なります。
ーー海外の法律と日本の法律では、どんな違いがあるのでしょう。
大まかに言うと、海外の法律は人権に対して非常にシビアですね。特に子供に関する表現は、多くの注意点があります。
実際にクリエイターの知人は、海外の生成AIのコンテストで、親子が出てくる映像をテストアップしただけで規約違反とされ、出場できなくなりました。
ーー本物と見分けがつかないほどリアルな映像ができてしまうぶん、厳しいルールが必要なのですね!
編集後記

いま、AIと所蔵権・著作権の問題は、クリエイターだけでなく世の中全体の関心ごとになりつつあります。大手企業の広告に第一線で関わっている木之村さんのお話は、職場や業務で生成AIを導入しているという方にとって、学びが多かったのではないでしょうか。連載最終回の次回は、AIの登場でクリエイターの仕事はどうなる?という疑問をぶつけてみました。乞うご期待!
▼同社のインタビュー記事を読む