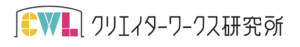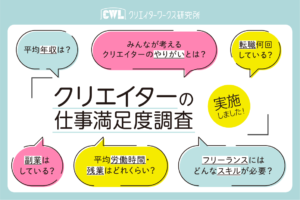常に“意図を考えながら作る”、それが次の発想のネタに
― まるこ
期待値を超えるパフォーマンスを出すために、やってらっしゃることってありますか?

― 川端さん
僕はこれをよく言うんですけれども、「できない人がオリジナリティを出したデザインを見せてこないで」と、僕はちょっと思っているところがあるんですよね。
― まるこ
できない人というのは?
― 川端さん
そもそもの技術が未熟な人もそうですが、物事の基準点からどこをどれだけ外すのかコントロールできない人ですね。
例えば雑誌の表紙を作ってくれと依頼されたときに、雑誌っぽいデザインってどんなものかっていうのが、頭に浮かばなければいけないと思うんですよ。
お味噌汁と言われたらこういうもの、ふわふわ可愛い女性用のワンピースと言われたらこういうものみたいな、それぞれの“THE王道”という基準のイメージがあるじゃないですか。
その基準点をすぐ思い浮かべられて、そのエッセンスを取り入れてちゃんと再現できる技術がまず必要だと思っているんです。
その上で、依頼されている商品独自の良さとか他社にはない強み、あるいは他社にはあるけどこの商品にはない弱みとかを見つけることから始まって、「THE王道と比べて、この商品をどう変換していくのか、差異を見つけていくのか」というところが、プロダクトのとの向き合い方やユーザーとの接点になっていくと思うんです。
敢えて全部王道から外すのか、一部分だけ王道なのか、ほぼ王道でいくのか。
そういう王道との距離感をコントロールができなかったり、外し方が分からないっていうような人が、自分なりのオリジナリティを出したものを作ってきても、良かった試しがないですね。
― まるこ
分かります、それは全くその通りですね。
― 川端さん
バナーの作り方もそうですよね。
例えば不動産のバナーだったら、通常こういうものだよねっていうのが何パターンかあって、その中で王道からズラしたものがあればいいんですけどね。
なんとなくマンションの写真にドーンと文字が飛んでいれば良いわけがなくて、そういうのを見ると、技術云々の前にスタンダードを知らないなというのがすぐ分かるので、それに対してフィードバックはできないです。
「まず調べてきて」と言うしかないですよね。
― まるこ
確かにリサーチが甘いまま、作業にかかっちゃう人は多い気がしますね。
― 川端さん
そこがそもそもダメなところなんですよね。
独学でスキルを磨くなら、何でも作れるようになるんじゃなくて、こういう風にすればこういうものが作れるのかなっていうのを身体と頭に叩き込んでいくのが必要で、そのために徹底的な模写は有効なんです。
何ピクセルのズレもないくらい模写すれば作れるようになるし、そういうことをしないまま、パッと見てふんわり作っていたら、その微妙な差に気付けないですよ。
1回プロが作った基本、ナショナルクライアントが出したようなデザインを徹底的に模写してみれば、これが基準なんだって分かると思いますよ、別のものを作ったときに「あ、違うな」と。
そこに気付けば、その差異を自分でコントロールできるようになります。
ただ作って終わりじゃなくて、「他とはどこが違うのか?」「なんでこの部分はこんなに目立つところにあるのか?」とか、「この大小の違いは何なのか?」と考えて作っていれば、このデザインになった意図が見えてきますから。
― まるこ
バナーだと「小さいサイズだからすぐ作れそう」とライトに捉える方も多いし、ふわっと作って終わり…な人も多いと思います。でも意外に奥が深いですよね、バナーは。
― 川端さん
自分でいろいろ作っていく繰り返しの中で、AとBのサイトのこんなところに差があったのかとか、こっちとこっちのキャンペーンに差がある理由はターゲットが違うからかとか、そういう違いが分かるようになります。そうやって自分の引き出しが増えていって、コントロールできるようになるんですよね。
深掘って考えたり作ったりした分だけ、次の発想のネタになっていくところなので、ここは自分のやった経験数に比例するものですけど。
そういう試行錯誤がないのに、「どうやって作れますか?」と聞かれても、僕からしたら「やってないからじゃないですか」としか言えないですね。
― まるこ
まずやりましょうよ!ってところですよね。やっぱり模写はいいんですね。
― 川端さん
そう思いますね、それが僕の独学の方法だったので。
― まるこ
ありがとうございます。当時川端さんがこうやって来られたというのであれば、説得力があります!
人と比べるのは当たり前。そこで感じる劣等感を原動力に
― まるこ
川端さんがインハウスでデザインをされていた当時は、インハウスデザイナーというのはまだまだ少なかったのではないかなと思いますが、その頃、自分の周りのデザイナーと比べて不安に思ったことはありますか? また、ブレずに自分のデザインを追求していく方法みたいなものがあったら、お伺いしたいです。
― 川端さん

いや、数年程前までずっとブレブレでしたよ(笑)。
インハウスでデザインをやっていたのは26歳くらいの時ですが、インハウスデザイナーだったわけではなくて、業務としてデザインを作ってただけなんですよ。
当時は「どうすれば自社の売上に貢献するクリエイティブを作れるか」しか頭になかったので、他のデザイナーと比べて劣等感を持つということはなかったし、僕以外に作れる人がいたらいいなぐらいしか思ってなかったですね。
― まるこ
そうでしたか、なるほど!
― 川端さん
ただnanocolorを起業してからは、それまでが独学でやってきたこともあって、お客さんが制作会社に求めていること、制作会社として提供しなければいけない品質のスタンダードがこれでいいのか?という正解が分からない不安はありましたね。
そして、僕が作るということは、会社の代表が作ったデザイン、すなわちトップラインなんですよね。そういう位置づけでお客さんに提案するプレッシャーもありますし。
世の中のデザインを見れば、技術においても表現力においても、自分よりも優れてるものが山のようにあって、「世の中には僕以上のものばかりだ」と思うくらい、比べるしかなかったですし、デザインの学校に行こうか…とか思ったときもありました。
今のデザイナーの皆さんも比べて大変かも知れませんが、僕もずっと比べていたし、それが当たり前かなと。
今では僕はいわゆる安心材料としてデザイン以外のこともやってますが、そこに辿り着いたのが結局36、7歳ぐらいだったかな。
― まるこ
川端さんでさえ、人と比べて不安になったりすることもあったんですね!
― 川端さん
あります、ありますよ。
でもそうやって比べて、自分はまだまだだなと思わなくなったらおしまいかな、というね。
潰されるプレッシャーと向き合うことも、デザイナーの仕事の大事なところでもあるので、そこから逃げずに。
今話してて思いました。もしかしたら僕がプレッシャーを感じる量と数は、他の人よりも多かったのかもしれないですね(笑)。
デザインを習ったこともないくせに、制作会社を立ち上げて、自分で作って提案するっていう正解のない世界だったので。でも自分で自分を褒めるなら、プレッシャーのおかげで得たものっていうのはあったかも知れないですね。
― まるこ
比べるのは当たり前だし、そこでプレッシャーを持ちながらやることがデザイナーの仕事!というお話もすごく納得感があります。
― 川端さん
人によると思いますけど、僕の場合は人と比べて生じた劣等感が、ある意味原動力になりました。
そのときの自分を肯定することはなかったですし、全然できてないという意識が圧倒的に多かったので。
ただ一つきっかけとしてあったのが、最初の頃は「何となくできてない…」としか思えなかったんですけれど、あるとき「自分のできてないところ」と「分かってないこと」が明確に見えてくる瞬間があって。あ、ここが足りてないんだ!ここが分かっていなかったんだ!と理解できた瞬間に、僕はすごく晴れやかになった気がします。
自分に足りないここを身につければ、今まで不満足だった部分が解消できる!というのが明確になればなるほど、すごくマインドとしてはスムーズになりましたね。
― まるこ
ものの捉え方がとてもポジティブで、素晴らしいです!
デザインスキルを磨く上での心構えがとてもよくわかりました。ありがとうございました!

▼次のインタビュー記事を読む
編集後記

連載1回目は、川端さん流 デザインスキルの習得方法についてインタビューを展開してきましたが、いかがでしたか?
「徹底的に模写をする」という方法は、川端さんのお話を聞いていくうちに「デザインのテク」だけでなく「深いリサーチ力」も身につくということも分かりました。
そのリサーチにこだわっていくことで、マーケティングの知見も自然と身についていくのだと思いましたので、ぜひ参考にしてみていただければと思います。
連載2回目は【クリエイターが仕事を続けていくために必要なこととは?】についてのインタビューをお送りします!
フリーランスや起業を目指しているクリエイターにとっても興味深い内容となっていますので、こちらもぜひお楽しみにしていてください。