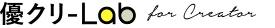バルト海を挟んだ対岸にフィンランド、大陸の東側にロシアという立地の「エストニア」。人口わずか130万人の小国ですが、実は、あの『Skype』発祥の地で、欧米では「世界屈指のデジタル先進国」として知られる国です。近年、日本企業もエストニアのベンチャー事業に注目し始め、すでに投資が始まっている状況です。今回は、日本ではあまり知られていないエストニアのデジタル分野の成功術、そこから日本のクリエイティブ業界が活用できそうなヒントを探ります。
目次
■小国エストニアが欧州をリードする「デジタル大国」になるまで
バルト三国の中でもエストニアは、ハイテク・デジタル産業で各国のリーダー・大学関係者・企業家から熱い視線を集めています。しかし、このような小国がいかにして注目を集めるようになったのでしょうか。
まず、1991年に旧ソビエト連邦からの独立以来、エストニアは「経済近代化の改革」へ迅速に乗り出しました。特徴としては、スタート時からデジタル化へのアプローチを取ったことが挙げられます。
最初は教育から開始され、エストニアでは2000年までに“すべての教室”にコンピュータを設置、すべての学校でオンラインシステムを確立しました。政府は人口の10%に当たる「成人」に対しても、無料のパソコン教室を提供しました。
こうした改革によって、将来のデジタル社会において活躍できる人材を育成・確保することができました。
そして、2002年にはハイテク技術を用いた「国民IDシステム」を構築。IDカードにもデジタル署名機能を付けることで、税金のオンラインによる支払いやオンライン投票(エストニア国民の3分の1が利用)、医療ケアのデジタル記録、オンラインバンキングなどが利用できるようになりました。
この動きがすべて2000年初頭の出来事なのですから非常に驚きですね! 現在、エストニアにおいてオンラインで「できないこと」は、入籍・離婚手続き、動産売買の3つだけだと言われています。
旧ソ独立後のインフラ構築の開始段階から、エストニアはインターネットとテクノロジー導入に乗り出すことによって、ビジネスのみならず、あらゆるものがインターネット(オンライン)へ移行していく未来にいち早く気がつき、ヨーロッパのデジタル化へのロールモデルとなったのです。
エストニア大統領カリユライド氏は、CNBCのインタビューで
『エストニアは比較的貧しい国でした。政府も公務員も、国民に質の高いサービスや公共事業を提供することを望んでいたので、真っ先にデジタル導入に踏み切りました。単純明解に、それが低コストで簡単な方法だったのです』
と、語りました。

■ビジネスの出発点になる『E-residency』などで産まれる新しいチャンス
上述のカリユライド大統領は、さらに下記のように語っています。
『E-School(電子スクール)システムを確立し、学校におけるデジタルコミュニケーションが可能になったことを肌で感じながら成長する世代を生み出しました。E-Health(電子ヘルス)による医者も然り。通常、民間セクターだけが可能なサービスをエストニア政府は提供しています』
現在、日本でも進められている「先進技術の情報収集・人工知能(AI)・サイバーセキュリティ」においても、テクノロジー戦略に長けたエストニアの先行例が、デジタル社会を実現するための必要ノウハウを学ぶことが可能かもしれません。
そして、エストニアにおける「キー」となるフィーチャーが、2014年に導入された『E-residency(電子居住者)』です。これは、エストニアには居住しないで他国からビジネスの起業を認めた世界初のシステムです。
このプログラムによって、EU内でのチャンスを探している企業の出発点となりEUの単一市場によるベネフィットも享受できるため、その申請人数はすでに50,000人以上(2019年時点)となっている状態です。
E-residencyの成功を受け、エストニアではさらに「デジタルノマド・ビザ」を打ち出しました。このビザによって、世界中から遠隔で働く雇用者を可能にし、公共と民間の枠を超えたパートナーシップの例としても注目されています。
■日本企業も注目するエストニアならではの「スタートアップ企業の誘致」
E-residency、デジタルノマド・ビザに加え、ビジネスにメリットがある「税率」が世界各国のスタートアップを引きつけています。
エストニアは、今や一社当たり1兆ドル(約1077億円 2019年6月現在)以上の価値があると言われる数々の民間企業やスタートアップの拠点となっています。実は、あのSkypeも2003年にエストニアで設立されたスタートアップ企業。現在ではこうした投資がITに限らず、オーガニック食品の開発など、多岐の分野に渡っています。
そして、今年に入って日本企業もついに動き出し、国際協力銀行(JBIC)が1月に「ホンダ」、「オムロン」、「パナソニック」などの日本メーカー、およびエストニアのベンチャーファンドとともに、人工知能やサイバーセキュリティー、モノのインターネット(IoT)などの先進技術分野における投資ファンドを立ち上げました。
続いて「丸紅」も4月に首都タリンに先進技術の拠点として出張所を設立、6月にはコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)を設立したのです。
日本文化独特の感性やクリエイションはEUでも人気を博している部分があり、熱烈なファンも少なからずいます。エストニアのこれらの起業チャンスはクリエイティブ業界においても利用価値が高く、他国の文化や発想を学ぶ材料や自分たちのクリエイションを広めるチャンスになるのは間違いないでしょう。
そして、働き方改革や人手不足でなどで揺れている日本の現状やクリエイターの働き方に一石を投じることもできそうです。
日本のクリエイティブ業界でも、先を見据えた迅速な対応で、うまく低コストのテクノロジーを導入した“先見の明”、および新しい取り組みを恐れない、一般概念の枠を超えた“パートナーシップ” など、エストニアが行ったこれらのことから学べることは多いはずです。

■まとめ
このようにエストニアの成功事例を見てみると、国をあげて次の時代を読み取り、未知の領域に果敢に挑戦した結果、他国などの競合たちから大きくリードした好事例と言えます。現在・未来と起こるであろう変化を予測し、見逃さず、そこへ向かうフットワークの軽さは、クリエイターとして、業界として長く生き延びていくために身につけるべき要素ではないでしょうか。